居心地の良さが決め手、生徒から教師へ
――KECに入社したきっかけを教えてください。
実は私自身がKECの生徒だったんです。とにかく雰囲気も居心地も良かったので、大学生時代のアルバイトも迷わずKECを選びました。アルバイト講師でしたが、時間割作成や生徒の学習指導など、授業以外の教室運営を間近で見る機会もあり、「教育分野って面白いな」「KECで教育にもっと関わりたい」と実感。そのまま新卒で入社を決め、現在15年目です。生徒時代から考えたらもう24年間、KECにいることになります。
算数・数学を担当し、小学4年生から高校1年生まで教えています。生徒と一緒に考えを深めながら、思考の手順や方法を増やしていけるところが数学の面白さ。この楽しさをわかってもらえるよう、授業に工夫をこらしています。しかし、もし再び教科選択をするなら、ロジカルな言語システムがある英語を教えてみたい気もします。知識も重要ですが、思考方法そのものを教えるのが好きなんですね。また、教室の責任者として、時間割作成やクラス編成なども任されています。
発達段階に応じた目標設定を大切に
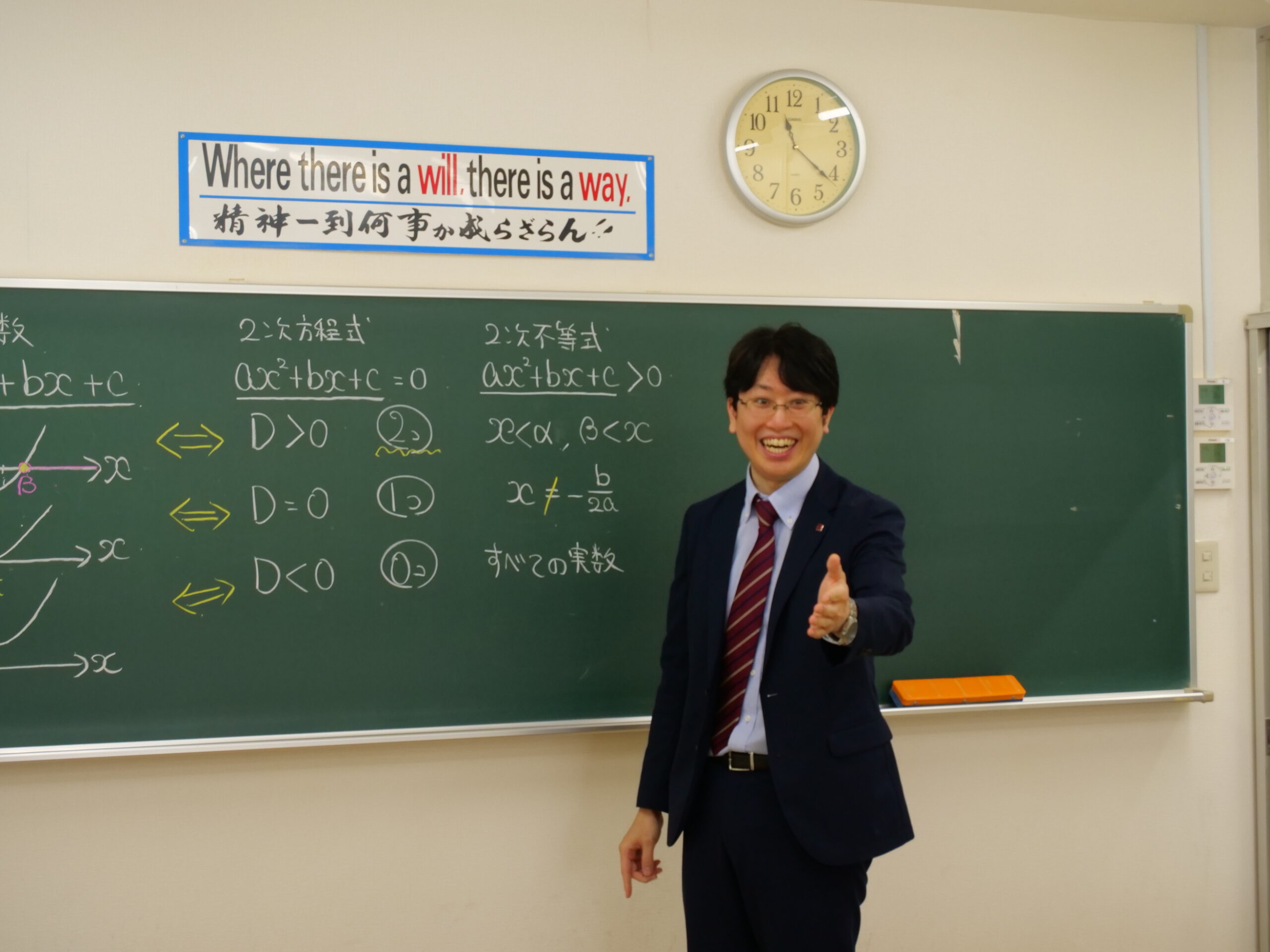
――小学生から高校生まで幅広い年代を担当されていますが、それぞれの年代で生徒の目標設定の仕方は違うのでしょうか。
小学生の場合は、正直なところ目標設定が難しいですね。保護者の意向が強く、まだ本人の目標というのは見えにくいんです。だからこそ、授業自体を面白くすることを大切にしています。勉強は好きじゃなくても「塾に来るのは楽しい」「学校の勉強が楽になった」と思ってもらえればいいですね。
中学生になると、やはり定期テストが一つの大きな目標になってきます。ただ、この年代は、大人の論理に反発心を抱く生徒も多く、本当に難しい。また、なぜ目標から外れてしまったのか分析しようにも、こちらに全然わからないような部分で、突然心が折れてしまうことも多い年代です。ですから、まず生徒の話をしっかり聞き、信頼関係を築くようにしています。本音で話せるようになってから「なぜそうなったのか」「これからどうするか」を一緒に考えないと、なにも伝わりません。
高校生の勉強は、自分で頑張れる力がないとしんどいと思います。しかし、高1、高2のうちは方向性や目標を見つけにくく、むやみに焦ってしまう生徒が多いです。ただ、この時期に具体的に動き出せていると、高3になってから変に迷わずにすむので、まず自分で調べてみようと促します。興味のある分野について、どの大学にどんな学部があるのか、それぞれの特徴は何かを調べます。「いいな」と思った大学は、実際に訪問したり、SNSをフォローしたりして、接点を作るんです。そのプロセスの中で、より具体的な目標が定まっていくことが多いですね。
――目標達成のためにどのようなサポートをされていますか。
最終的には生徒に「これから何をするか」を決めてもらうんですが、ここで終わりにはしません。例えば「漢字を3回ずつ書く」と決めたとして、その3回をどうやってやるのかまで一緒に落とし込んでいきます。生徒の性格や現状によって、うまくいく方法は違いますから、できるだけ細かい部分まで一緒に考え、その生徒に合った計画を立てるようにしています。
「一緒に考え、実行する」目標達成エピソード
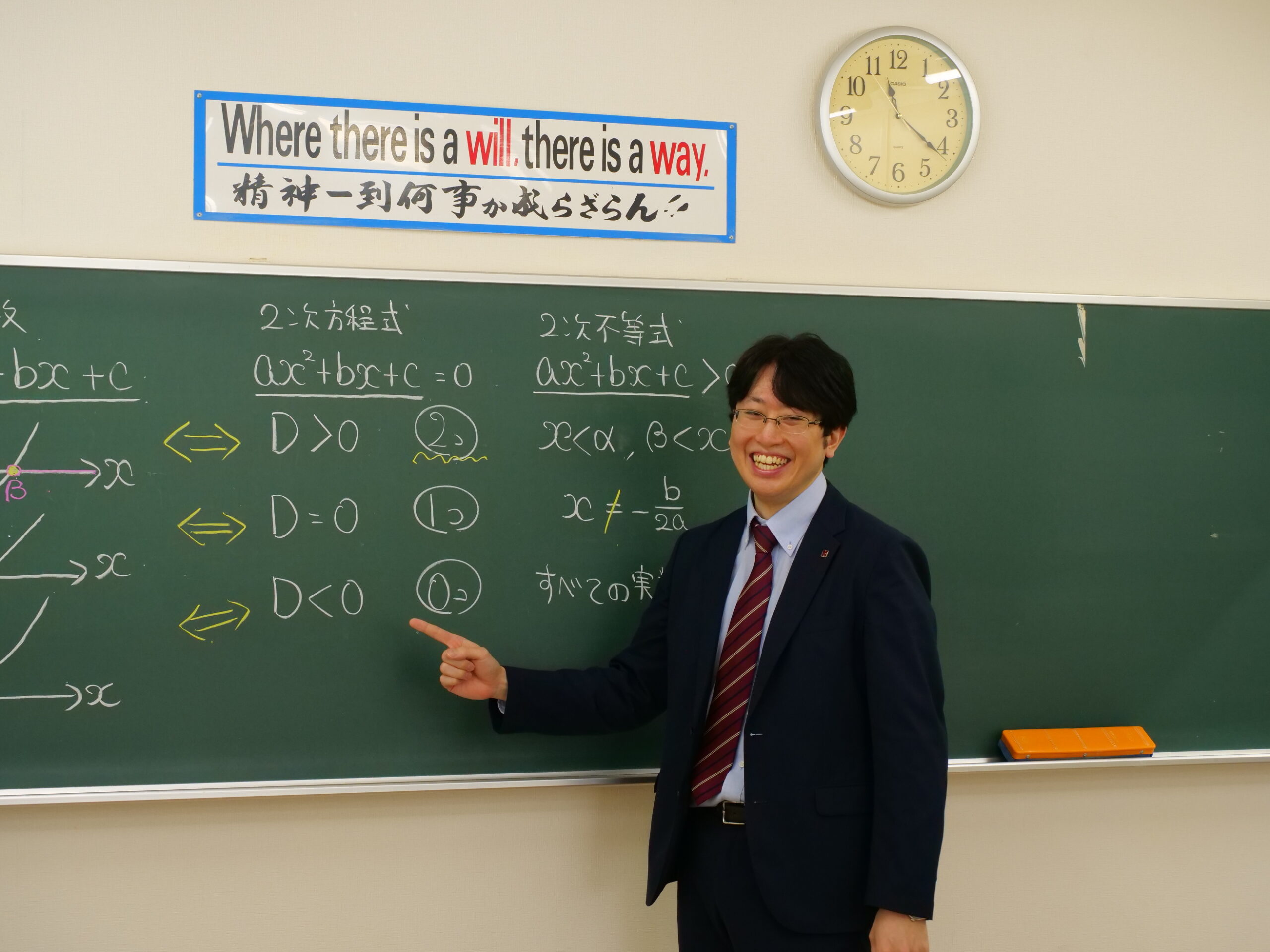
――印象に残っている生徒さんのエピソードを教えていただけますか?
直近では、定期テストの5教科合計点が200点台前半だった中学生が、340点台まで点数を上げた例があります。この生徒の場合、目標とやることは決めるんですが、なかなか実行に移せないんですね。そこで、2日か3日に1回のペースで授業や自習に来てもらって、その都度何をどこまでやれたか報告してもらいました。つまづいた部分は、教科の先生と一緒につぶしていき、パーソナルトレーニングのような形でサポートしました。
また、機を逃してはいけないサポートという点では、高校受験で不合格になる生徒のケースでしょうか。この場合は「すぐに塾においで」と声をかけ、面談をします。生徒はもちろんどん底に落ち込んでいますから、しっかり気持ちに寄り添いつつ、ただ「このせいで3年後も潰してしまうのはもったいない」「3年後に必ず良い結果を出そう」と、真剣に話をしたんです。実際にしっかり切り替えて、今春、第一志望の大学に合格した生徒がいます。本当にほっとしましたね。
誰も取り残さないサポートを目指して
――教育現場のトレンドも変化していく中で、今後どのような取り組みをしていきたいですか。
当たり前ですが、生徒は一人ひとりそれぞれ個性があります。こちらが画一的な対応をしていては、生徒を伸ばしていくことはできません。しかし、自分から気軽に事務所に来ておしゃべりするような生徒は、状態を把握しやすいですが、そういうコミュニケーションが苦手な生徒もいます。気づくと帰ってしまっているような、そういった生徒とも、同じレベルまでコミュニケーションが取れるよう、もっと工夫ができるのではと感じています。例えば、今はスマートフォンも当たり前になっていますから、それを活用して家でもやり取りができるようにするなど、もう少し効率的な仕組みができないかと考えています。
――KECでは先生としてどのような人材を求めていますか?
教えるのが好きなことはもちろんですが、それ以外の部分も見られる人が良いですね。授業だけでなく、その子の将来がどうなっていくのかに関心を持ち、成長を一緒に喜べる先生であってほしいです。また、まっとうに教室運営をしていくためには、数字的なものを追いかけることも必要になってきますので、そういった経営面にも興味がある方が向いているかもしれません。
――最後に、教育者としての信念をお聞かせください。
生徒には「自分で考える力」をつけてほしいと思っています。数学などの教科においても人生全般においても、教えられた通りにやるだけでなく、自分なりの考え方ができるようになってほしい。そのために、まずは授業が面白くなるよう、また「考えるって楽しい」と感じてもらえるよう、工夫しています。これはKECの理念でもあります。考える手順や方法を自分の中で作れるようになることが、その後の人生でも大切になってくると考えています。




