エンジニアから教育者へ新たなキャリア
――京都大学工学部を卒業後、エンジニアとして働かれていたそうですね。
新日本製鉄(現・日本製鉄)で、約11年仕事をしていました。商品開発に近い仕事を4年ほど、品質管理を1年ちょっと経験しています。でき上がった商品の品質確認や、新商品の製造可能性の判断など、技術職としてさまざまな業務に携わりました。
転職を考えた理由は2つあります。1つは、長男としていつか故郷の関西に戻りたいという想いがあったこと。当時の配属先は千葉県の工場か東京の本社のどちらかで、関西での勤務は難しかったんです。もう1つは、バブル崩壊後の世の中の流れを受けてコスト削減が厳しくなり、研究の面白さを感じづらくなってきたことです。
――なかでも予備校講師という道を選んだのはなぜでしょうか。
実は、大学に入学した頃は、教員になろうと考えていたんです。教職課程を選択し、高校理科の教員免許を取得しました。ただ、大学生活の中で視野が広がり、4年生で教育実習に行く頃には既に就職先も決まっていたんですね。結局、新卒時は教員にはなりませんでしたが、そういったバックグラウンドもあって、教えることへの抵抗感は全くなかったんです。
転職を考えていた当時は家庭教師が圧倒的に多く、個別指導塾の形態で教える塾はほとんどありませんでした。いくつかの選択肢の長所短所を比較して、教えるという仕事に魅力を感じ、予備校教師の道を選びました。1995年12月に前職を退職し、3週間後の1996年1月にはKECでスタートを切りました。
生徒の可能性を引き出す指導哲学

――授業を行う上で、特に大切にされていることは何でしょうか。
教科指導のときも、日頃生徒と接するときも、常に心がけていることは、極論を言うとただ1つ、「生徒のモチベーションが上がる接し方をする」ということ。もうそれだけと言っても過言ではないくらい、そこは強く意識しています。
高校生を教えるというのは、大学受験で結果が白黒はっきりと出るところまで見届けるということです。どの生徒にとっても最良の結果が出てほしい。30年以上先生をやっていますが、毎年それはもう、祈るような気持ちですね。でも、30年教える中で、はっきり見えてきたこともあります。それは、懇々と「数学のベクトルが・・・」などと教えるより、生徒のモチベーションが最高の状態で自ら取り組んでくれる方が結果がいいということ。本人が気合を入れて取り組むことが、何よりも大切なんです。
――具体的にはどのような接し方をしているのですか。
実際の話、最初から勉強が大好きという生徒は、めったにいません。そこに火をつけていく必要があるんです。まずは生徒に「この志望校なら、このペースで、この時期にはこれぐらい勉強するのが一般的だよ」という話をします。そして、生徒本人に、不安な点がないか、見通しとしてできそうか確認したり、どんな進め方をイメージしているか聞いたりと、じっくり意見を引き出します。こちらから示すのではなく、あくまで生徒自身が考えて行動できるようなコーチングのアプローチに近いかもしれません。
「こうすべきだ」「我慢して勉強しなさい」といった、上からガツンといく指導をしないのは、生徒本人の将来の幸せのためです。自分の人生は自分で切り開いていかないといけません。自分で決断した目標に向かって、行動する力は必要です。その意味で、生徒自身が主体的に考え、行動できるようになってくれた方が、みんな幸せになれると思っているんです。
基本を大切に効果的な指導を
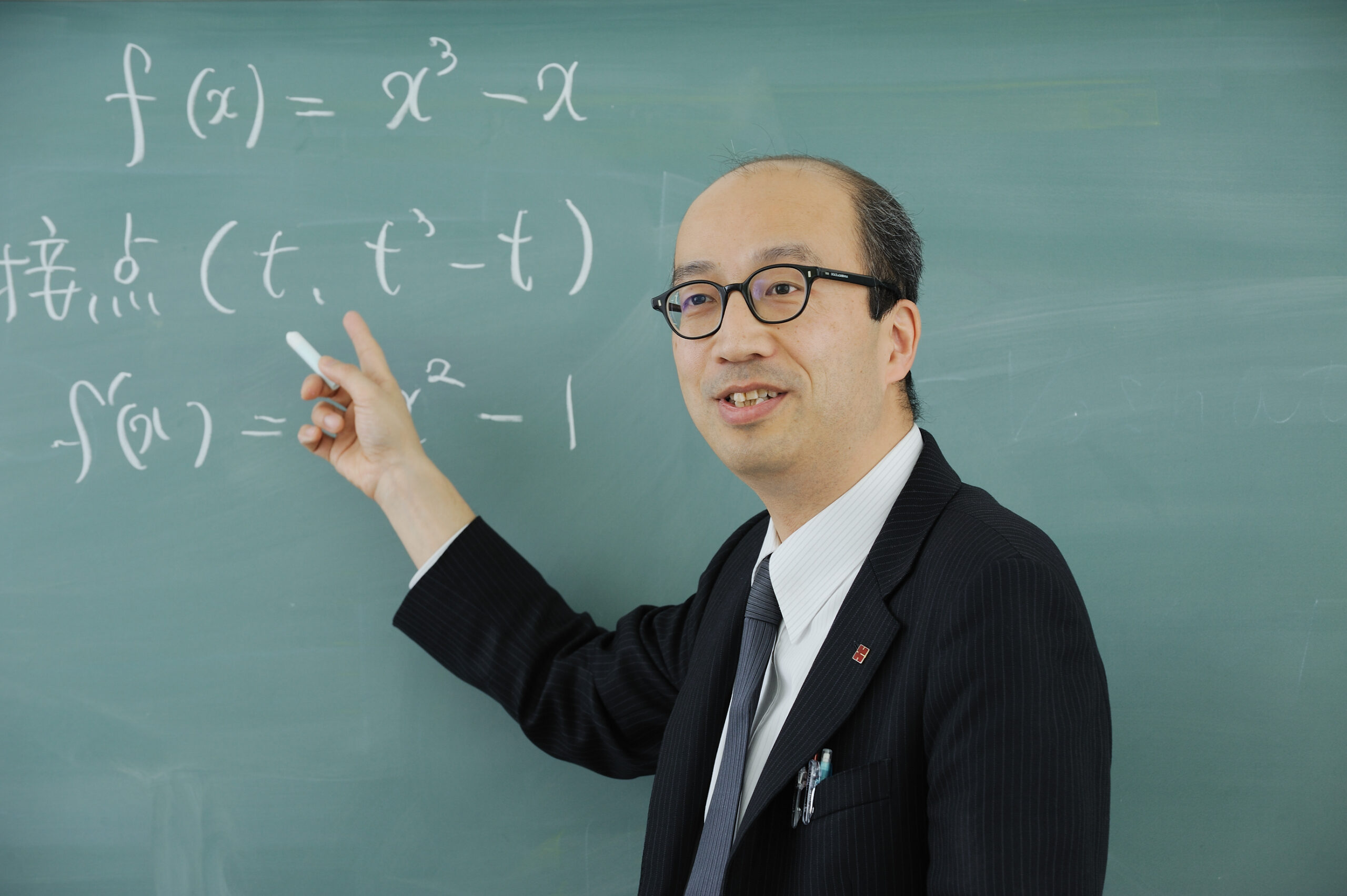
――数学を教える上で、特に意識されていることはありますか。
基本をしっかり理解してもらうことを大切にしています。基本がわかっていれば、少し違う問題でも応用がきくようになるんです。1つの学習で3問解けるようになる生徒と、1問しか解けない生徒では、これからの伸び方に大きく違いが出てきます。
しっかり理解しようとすると問題を解く速度は遅くなります。よく「次のテストまでに50問解いて提出」といった課題が出ますよね。答えを見て「ふんふん、そうか」と思って書いていくのと、「なんでこうなるんだろう」「これはどういうこと?」と考えながらやるのとでは、後者のほうがはるかに時間がかかります。しかし、完全に理解した後はどうでしょうか。応用問題が出ても、つまずくことなくスイスイ解けるのは後者です。
ただ、生徒としては、できるだけさっさと課題を終わらせたいと思うでしょう。気持ちは分かりますが、「入試のことまで考えたら、基本は大事だよね」と話しています。特に、理系を志望する生徒には、特に基本からじっくり取り組むことを勧めていますね。
数学に苦手意識をもつ生徒は多いものです。しかし、ほとんどの場合「やってないだけ」。真面目な生徒でも、よくよく聞くと、数学からはやや逃げ腰です。意識を変えて、真正面から取り組むことです。そうすれば、絶対に何とかなります。
変化する時代における塾講師の役割
――塾講師として働く魅力はどんなところにありますか。
学校の先生とは異なり、ちょっとクセがあっても効果的であれば、独自のノウハウをもって指導できる点ですね。例えば、授業では同じ生徒を意図的に何度も指名することがあります。ここをしっかり身につけてほしいと思ったとき、3回くらい連続で当てることもあるんです。学校ではなかなかできない指導の仕方ができますね。
――KECの教育体制について教えてください。
指導教科を越えたチームでの教育を大切にしています。特に大学受験に関しては、それぞれの校舎や現場のカラーに合わせた指導ができる体制が特徴です。
また、情報共有も重視していて、推薦入試の結果や入試動向について、本部から頻繁にアナウンスがあります。例えば、2025年の共通テストに新設される教科である「情報」は、早い段階から対策を進めてきましたし、私自身も講座を担当しました。このように、組織としてサポートしてくれる体制は非常に整っています。
――KECで働く良さはどんなところでしょうか。
根底に、確固とした「生徒のために」という精神があることですね。これは先生だけでなく、バックオフィススタッフもチューターも、しっかりと全社で共有されている価値観です。各先生がそれぞれの個性を活かしながら、生徒のことを第一に考えて奮闘している。そういう現場の雰囲気のおかげで、私も定年後もやりがいをもって働けています。幅広い年代のさまざまな個性の先生が活躍しているので、教えることに興味がある方はぜひ、仲間に入ってほしいですね。




