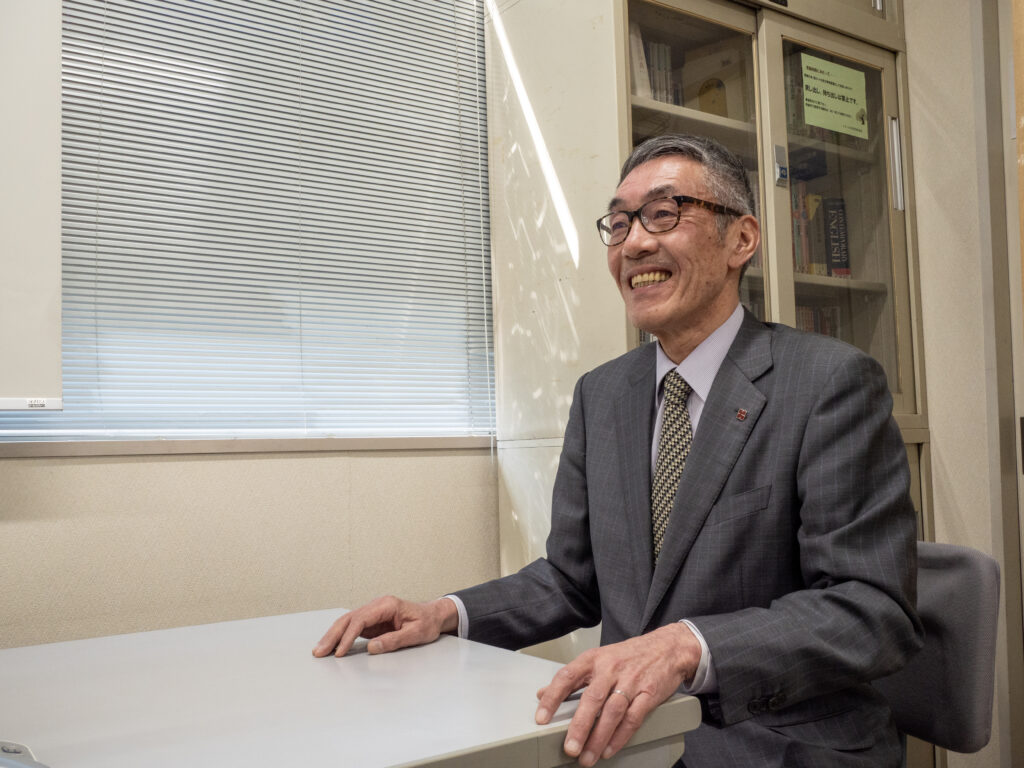「まずは行動」と背中を押す。
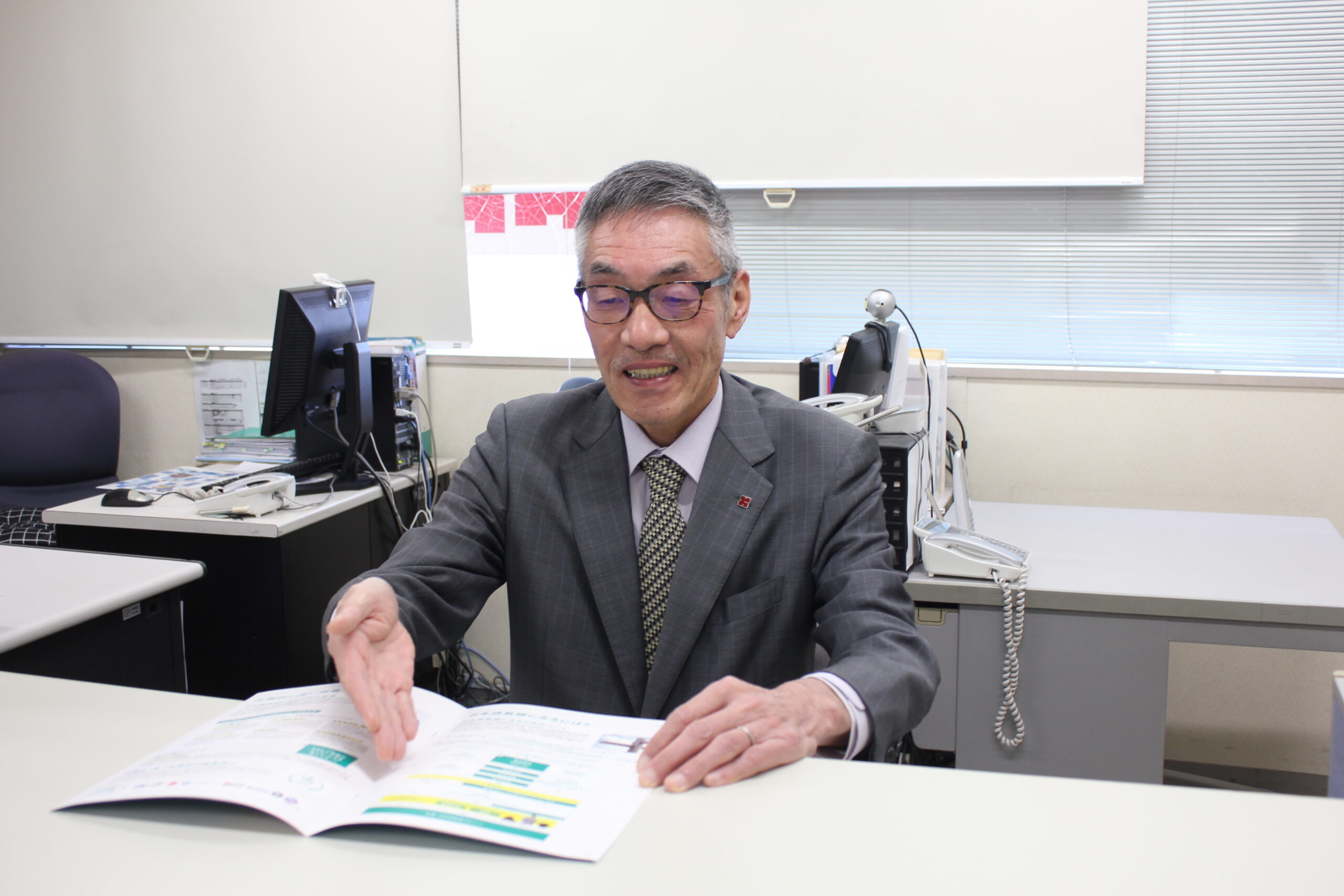
――現在の業務内容を教えてください。
日本語教師になりたい入学希望者に向けて当校の説明をする業務から、生徒の悩み事に対するアドバイスや履歴書の添削、キャリア相談など「在校生のサポート」を一貫して担当しています。入学希望者と在校生のサポート、どちらかに比重が傾かないように心を砕いています。既存の生徒に対して「期待されている以上のサポート」を追求することこそが、新たな生徒への最良のアプローチだと考えているんです。
生徒から多く寄せられるのは、まず「授業期間」の相談ですね。受講していくなかで「早期に修了したい」「ゆったり学びたい」といった要望をヒアリングし、生徒にあわせて調整していくイメージです。あとは、修了が近づくと「就職先」についての話が増えてきます。日本語学院として情報発信をしているのですが、最終的に迷って「どっちの方がいいでしょう?」といった相談を受けるケースは多いです。そのときは、生徒の相性などを鑑みて、長年の経験からアドバイスをしていますね。
――生徒から就職先を相談された際、どのように対応されているのでしょうか。
「行動が重要である」ということをよく伝えています。相談にくる生徒は慎重な方が多いので、例えば「今すぐ就職のための書類を準備してみましょう」など、一歩踏み出せるように強く背中を押すのが私のスタンスです。まずは動いてみて、そこから考えることの大切さをアドバイスしています。また、結局のところ「行ってみないとわからない」ことも多いです。職場となる日本語学校に、積極的に見学にいくことをおすすめしていますね。どんなによい日本語学校であっても、人によって感じ方は異なるものなので、必要に応じて行動量を増やすことが肝要です。
修了生に対しては、当校では一生涯の生徒だと考えており、「気軽に立ち寄れる居場所」でありたいと考えています。実際に海外に渡航し「帰国したので、就職先を探している」という方や、数年後に「履歴書を見てほしい」と訪れる方など、修了生との交流はずっと続いています。
――業務の中で、特に配慮されていることはありますか?
一般的な学校とは違い、多種多様な方が入学されます。社会人や大学生、年代も最年長で80代、最年少で高校3年生という生徒もいました。「日本語教師になりたい」という想いは1つですが、バックボーンやキャリアが違うので、例えば「同じ言葉」を使っていても「受け止め方」が違う場合が出てきます。そのため伝え方や表現の仕方には神経を尖らせていますね。
「就職が決まった」「実践で役立った」の声が、至高の喜び。

――生徒と接する上で、重視していることは何でしょうか?
一人ひとりと真剣に向き合い、受け身ではなく先回りするように「能動的に動く」ことです。また、「対応に神経を注ぐ」ことは大切ですが、一方で本人のために必要なことはブレることなくストレートに伝えるようにしています。あと、実は「熱心過ぎる場合、ブレーキをかけてあげる」ことも意外に重要です。一生懸命なのは素晴らしいことなのですが、例えば99点を取っているのに、「100点じゃない」と落ち込むような完璧主義の生徒もいます。
そんなとき「あまり、肩の力を入れ過ぎないように」と声をかけるようにしています。というのも、就職して現場に出たとき「常に満点」ということは少なく、むしろ多少のマイナスがあってもリカバリーしたり、それを活かして前向きに行動することが求められるので、「完璧主義で落ち込んでしまう」というマインドでは、本人が困ることになるからです。
――仕事でやりがいを感じる瞬間や、楽しいと感じるところを教えてください。
やはり一番うれしいのは、生徒からの「就職が決まりました!」という喜びの声ですね。また、働き出してから来てくれて「ここで習ったことが役立ちました」という話を聞くと、大きなやりがいを感じます。当校では「実践的な力を身に付けてほしい」という方針があるので、実技の回数が多いカリキュラムなんです。その分、生徒にとっては苦労を感じることもあると思いますし、口には出さなくても「くじけそうになること」もあるでしょう。しかし、KECで苦労したことは、現場に出たときに必ず自分の糧になります。それが「役立った」と言ってもらえたときは、本当に仕事冥利に尽きます。
――仕事をするなかで大切にしている考え方はありますか?
利他の精神を重んじることです。といってもそんな大げさなものではなく、教育業界に身を置いて社会人経験を積むうちに、「誰かのために貢献することの方が、自分自身が満足できる」という感覚を自然と得るようになりました。「情けは人のためならず」の言葉通り、人に尽くすことで自然と自己実現に繋がっていますね。
あとは、生徒を「お客様」だと捉えないことです。言葉はもちろん選びますが本人の成長のために、ときには厳しいことも伝えます。「注意したら嫌われるかもしれない」と、誤魔化すことの方が生徒のためになりません。それが教育に携わるものの責任だと考えています。
「利他の精神」を大切にする、新しい仲間と働きたい。

――長年勤めているなかで感じる、『KEC教育グループ』の魅力は何でしょうか?
以前は講師としてKECの塾や予備校で教えていたり、外国語学校で教えていたりしたこともありました。しかし、ここ最近は京都校の所長の職務に専念しているので、グループ全体としてはお伝えしきれないですかね(笑)。ただ、グループの理念と私の考え方は共通していると感じていて、「利他の精神」「生徒としっかり向き合う」という考え方は魅力的だと思います。向き合うことなく「何かあっても、放っておく」方が、実は簡単です。しかし、そんなことでは「目の前の生徒が、就職に失敗する」という事態にもなりかねません。「言うべきことを伝えることが、親切であり、教育である」と確信しています。
――「京都校をこうしていきたい!」など、今後の目標やビジョンを教えてください。
「楽しい教室づくり」がビジョンです。授業や運営は、大変なときもあります。しかし、どんなときでも「笑いや会話の絶えない京都校」でありたいです。「授業は真剣に、勉強以外は息抜き」といった、メリハリのある教室を目指しています。ちなみに今の京都校はとても賑やかで、生徒同士も交流がありますよ。そのために私が特段意識してやっていることはないのですが、冗談ばかり言っているので、生徒たちからよくツッコまれています(笑)。今、京都校は授業は講師の先生が担当し、教室運営の管理業務全般は私が一手に担っています。そのため、生徒一人ひとりのことを把握できる体制です。
――ビジョンを叶える教室づくりに向けて、どのような方と一緒に働きたいでしょうか?
能力やスキルは一切問いません。「生徒一人ひとりと向き合いたい」「人を大事にする環境で働きたい」という方と一緒に働きたいですね。あとは、「洞察力」があると完璧ですが、現時点では持ち合わせていなくても人に対する興味があれば、自然と身に付いていくと思います。業務については実際にやってもらいつつ、レクチャーしますので、無理せずスキルアップできる環境で一緒に働きましょう。